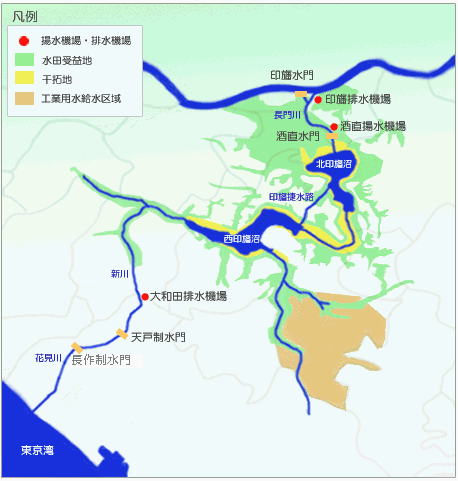
水資源開発機構による印旛沼事業
これまで、先祖梶野良材が勘定奉行であった時、最後に仰せつかった印旛沼堀割普請について述べてきたが、その後もこの地域の治水事業は不可欠とされ、国の事業として取り上げられてきた。今日では、“あばれ沼”と呼ばれた印旛沼周辺は面目を一変して新たな装いを以て環境にとけ込んでいる。この事業に関して、水資源開発機構が、ホームページに掲載しているので、その概要を紹介しつつ、梶野良材が目にしなかったであろう姿を天上の霊に捧げるつもりで紹介する。
昭和21年から始められた印旛沼開発事業は、近代的な工法と大型機械の導入することにより、治水を始め、農業用水、工業用水及び水道用水の多様な利水機能を兼ね併せた印旛沼に生まれ変わった。印旛沼は、農業用水、工業用水及び水道用水が安定的に取水が出来るように5月〜8月と9月〜翌年4月までの2期に分けて常時満水位を定め、酒直水門と酒直機場を操作して水位管理が行われている。
また、洪水時に利根川への自然排水が不可能と判断した場合には、印旛水門を閉鎖して利根川からの流入を防ぐとともに、印旛機場を運転して、洪水を利根川に排水している。それでも印旛沼の水位が下がらない場合は、さらに大和田排水機場のポンプを運転して、花見川を通じて東京湾に排水することによって、印旛沼周辺の農地や市街地等の洪水被害を防止している。
印旛沼周辺の水資源機構の施設配置
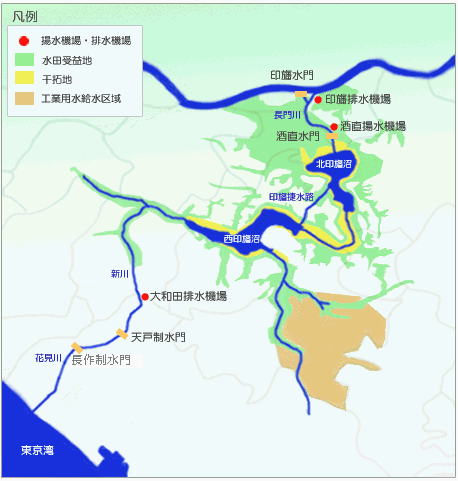
新川下流から大和田排水機場を望む

新川上流から大和田排水機場を望む
